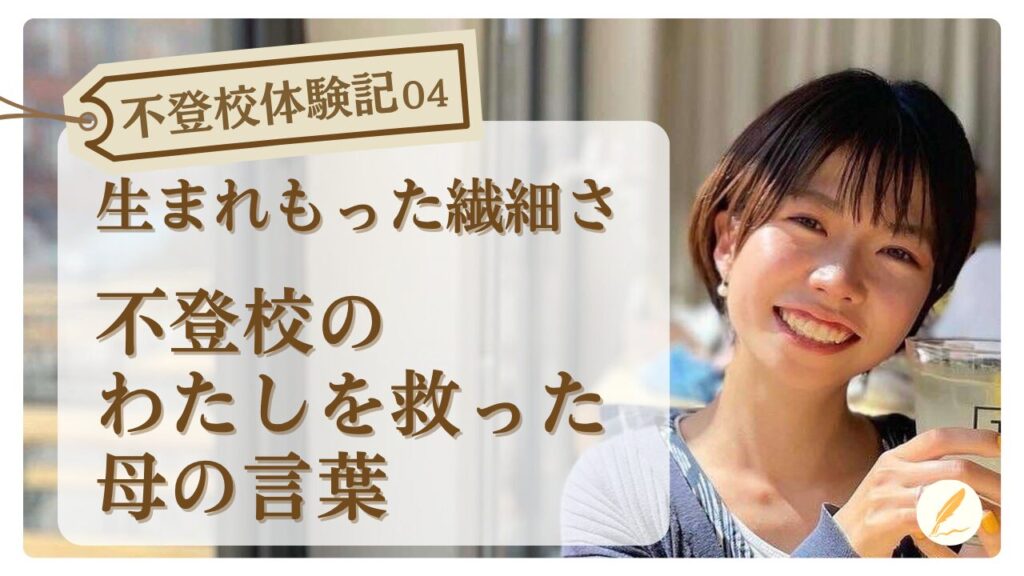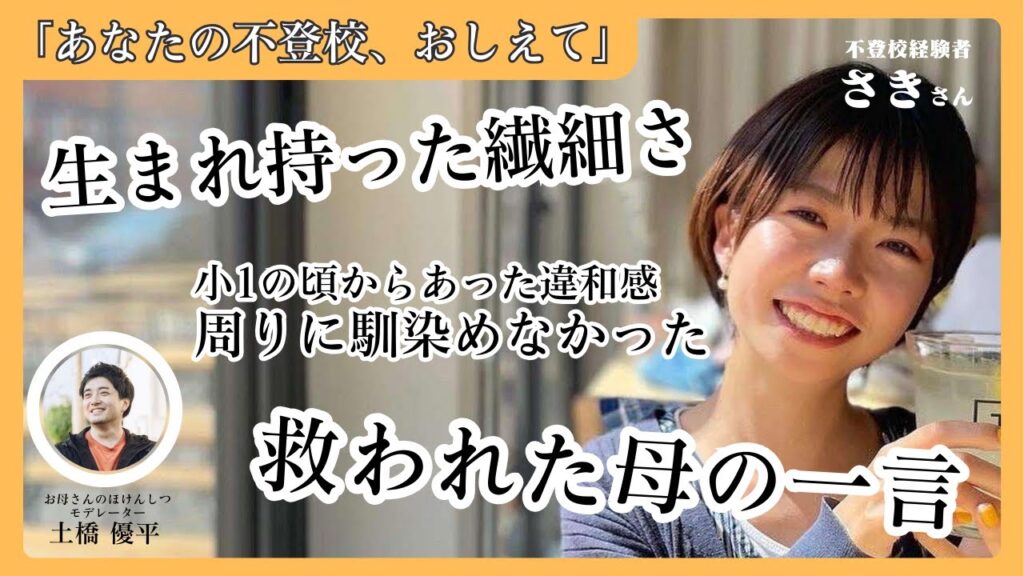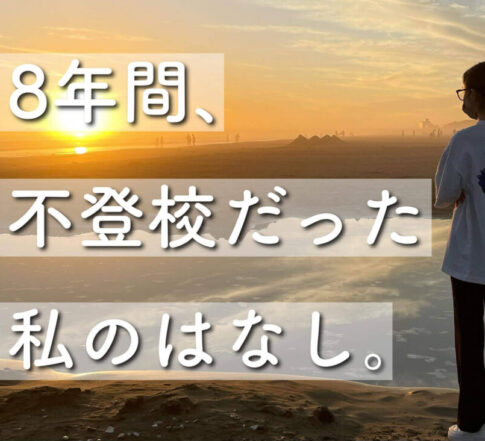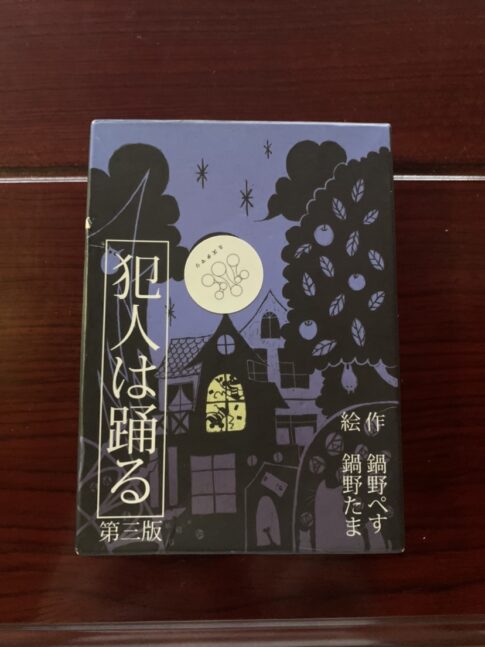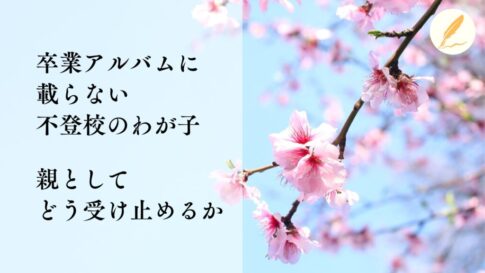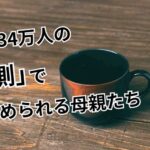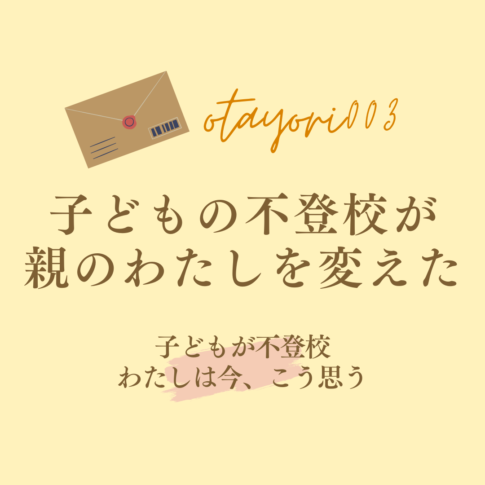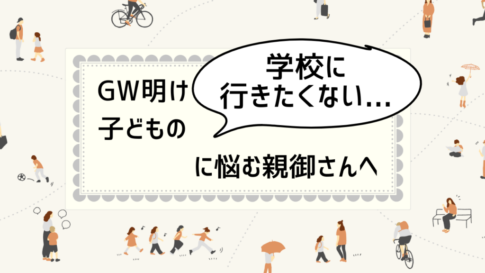Contents
敏感さから感じる小さな違和感
私は小さい頃から、人の感情の変化や空気にすぐ反応する子でした。幼稚園のときは自由に過ごせていたけれど、小学校に入ると「ここに座りなさい」「ここに〇〇を置きなさい」という決まりが多くなって、緊張しました。
プリントの配り方ひとつで注意され、給食袋の置き場所を間違えても注意される。「こんなに制限されるなんて…。どこまで自由に動いていいんだろう」と、子どもながらに思っていました。でも口に出せないので、熱や頭痛などで、体に出ることが多かったです。
不登校の理由と周りの大人の反応

中学二年の春、クラス替えがきっかけで学校に行くことがしんどくなりました。大きな事件があったわけじゃないけれど、クラスの雰囲気に自分を合わせるのが難しくなり、学校に行けない日が増えました。
両親からは「どうして行けないの?」「いじめ?」と聞かれました。でも、わたしの中には「言葉にできない苦しさ」があって、理由を説明できないことがつらかったです。父に無理やり学校まで連れて行かれたこともありました。泣きながら校門まで歩いたとき、「誰もわかってくれない。」と感じました。教室の前で足が止まることも何度もありました。保健室の先生に「病は気から」と言われた言葉は今も残っています。
体が拒絶した給食の時間
給食も大きなつまずきになりました。もともと食が細かったのですが、中一のころ、友達に「全然食べてないじゃん!」とからかわれたことで、給食がどんどん食べれなくなりました。私がどれくらいご飯を食べれたか何人ものクラスメイトがチェックしにくるのです。ある日のことでした。いよいよお箸を持つこともしんどくなりました。
「ここでお箸が持てなくなったら三年間食べられなくなる」
そう思いましたが、指が動かない。「あぁ…もう無理だ」その瞬間諦めました。辛かったです。そこから給食は牛乳だけになり、外食も人前で食べることも難しくなりました。家では普通に食べられるのに、学校では食べられない。友達と食べ物の話をすることも出来ない。

母親に連れていかれた病院で、お医者さんに「ご飯食べてる?なんで食べないの?食べないとダメだよ」と言われたこともとてもしんどかったです。背景を知ろうとしないのに、寄り添おうともしないのに、なぜ一方的にそんなことを言われないといけないんだろう。お説教めいた言葉を日々たくさんの人から言われ続け、私の心はどんどん遮断されていきました。
「その時に考えればいい」—救ってくれた母のことば

学校を休む日は、映画を見たり、絵を描いたり、日記を書いて過ごしました。とは言っても、そんなに優雅な日々ではなく、苦しさや悲しさをアートを通して発散していました。日記には、
「学校つらい」
「助けてほしい」
「誰もわかってくれない」
といった言葉が並びました。
「人なんて信じないほうがいい」「行かないのは逃げ?」と書いていたこともあります。読み返すと、そのときの気持ちがよみがえります。
先生と母親、それぞれの言葉
夏休みのある日、担任の先生から電話があり「体育祭が終わったら学校に来るって約束できる?」と言われ、胸が苦しくなりました。なんで向こうの都合で勝手に決められなきゃいけないんだと思いました。それでも「イヤです」なんて言えなかったので、力なく「はい」と答えました。
電話が終わったあと母に「どうしよう」と伝えると、母は「その時に考えればいいし、行けなかったら行けなかったで、行けたら行けたでいいんじゃない?」と笑いながら言いました。その一言で、力が抜けたのを覚えています。
正解を迫られないこと、ただ受けとめてもらえることが、本当に救いになりました。
母とはぶつかってばかりで、正直「何をしても怒られる」「何も理解しようとしてくれない」とずっと思っていました。だから学校へ行けなかった時に、少しずつ時間をかけて寄り添ってくれたこと、わたしが起きたタイミングでご飯を出してくれたこと、近くの公園でパン屋さんのパンを食べたことなど、「温かい日常を作ってくれたこと」が、何より一番ありがたく、嬉しかったです。

学校の中でも助けてくれる先生がいました。給食の時間だけ相談室で食べてもいい、と言ってくれたさわやか相談室の先生です。友達が誕生日に家までプレゼントと手紙を届けてくれたこともありました。「無理しないでね」と書いてあった手紙を何度も読み返しました。
「周りの評価を気にしない」が私を変えた
復帰は一気にはできませんでした。別室登校、短時間、好きな教科だけ。少しずつ、自分で選んで動けたことが積み重なっていきました。中三になる頃には、実験の授業で班の役割を果たせるようになり、友達と一緒に失敗や成功を分け合えるようになりました。その経験が勉強のやる気にもつながりました。中2で抜けた勉強も、中3で取り戻せました。
演劇で出会った新たな価値観
高校では演劇部に入ったことが大きな転機となりました。

部の方針は「芝居に正解はない、自由に意見を出していい」というものでした。自分の意見が自由に反映され、みんなで作品をつくっていくことが楽しかったです。ここで「自分の意見を言ってもいい」と思えるようになりました。
そしてそれらの経験から教育関係の仕事に携わったあと、退職をしてデンマークのフォルケホイスコーレで約半年間アートを学びました。そこには「NO COMMENT(評価しない)」というルールがありました。「上手い」「下手」と言われないことで、想像以上に自分と向き合い、自由に表現できるようになりました。
帰国後にアートセラピーに出会いました。今は放課後等デイでの指導や、オンライン家庭教師、カウンセリング、子どもアートサークルを開催しています。感受性の強さは生きづらさにもつながるけれど、人の小さな変化に気づける力でもあると、今は思えます。
いま足踏みをしているあなたへ、そばで迷う大人へ。
もし今、教室の前で足がすくんでいても、「行けない理由」を探さなくて大丈夫です。言えなくても、大丈夫です。まずは安心できる場所で過ごしてください。
家でゆっくりする、好きなことをする、信頼できる人とだけ話す。小さな「安心」や「楽しい」を積み重ねていくことで、少しずつ本来のあなたらしさが出てくると思います。だからまずは自分を責めずに、ゆっくり充電してください。
原因追求よりも大切なこと

保護者の方にお伝えしたいことは、わたしを支えてくれたのは受けとめの言葉と愛情を感じる時間だった、ということです。
「そのときに考えればいいよ」「今日は天気がいいからピクニックでもしよう」そんな言葉にわたしは救われました。
原因を追求するよりも、「そうなんだね」と受け止めてもらえることが力になります。
会話がなくても、同じ食卓を囲むだけで安心することもあります。「あなたのことを想っている」と言葉で伝えるだけでなく、一緒にのんびり散歩をする時間で、ココロが充電されることもあります。数字や偏差値、保証のあるなしではなく「ここなら呼吸しやすいんじゃないかな」と思える場所をお子さんと一緒に選んでほしいなと思います。
不登校を経験したから
絵、音楽、ゲーム、ものづくり。好きなことは必ず未来につながります。
話すのが苦手でも、几帳面さや集中力が生かせる仕事はたくさんあります。「この先、この子は大丈夫なんだろうか?」と考えすぎるより、お子さんの中にある強みやワクワクを信頼してください。
ネガティブな経験は無駄ではなく、自分の本当の場所を見つけるためのサインです。今ある小さな温かさに目を向けてほしい。それはお子さんだけでなく、保護者の皆さまにもお伝えしたいです。

不登校を経験していなかったら私は教育関係の仕事には就いていません。アートを通した支援もしていないと思います。母娘関係も最悪だったかもしれません。あの経験があったから、全て学びになり、プラスになっています。無駄なことはひとつもないなと感じています。だから皆さんも、皆さんの歩幅で、皆さんのままで大丈夫です。心から応援しています。
この記事の主人公をご紹介

▼さきさんには、当時の経験談などをYouTubeライブで伺わせていただきました。ご覧になりたい方は画像をタップ。